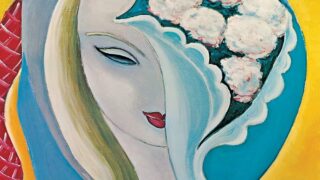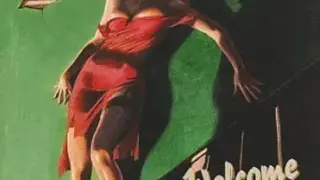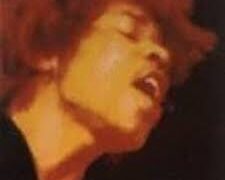ROCK
ROCK Rolling Stones [Their Satanic Majesties Request]
1967年12月に発売された6枚目のスタジオアルバム。初のセルフ・プロデュースであり、アメリカ、イギリスで同一の内容となる初の作品。当のメンバーが酷評するアルバムであるが、曲単体で見れば彼らも認める通り"She's a Rainbow"や"2000 Light Years From Home"等のカラフルでサイケデリックな曲を収録された作品です。決して名盤ではないかもしれないが、変なジャケットを見ながら年に一度は通しで聴きたいアルバムです。